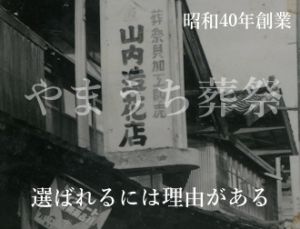矢印のボタンを押すとラジオドラマの音声が流れます。
介護士モノローグ(以下M)「僕が訪問介護のヘルパーとして山崎のおじいちゃんの家に通うようになってから、もう三年が経つ。おじいちゃんは腰が悪く、一日の大半をベッドで横になって過ごしている。入浴や食事といった毎日の生活の補助が僕の仕事だ」
介護士「じゃあおじいちゃん、起きますよ。よっこい、しょ」
山崎 「痛い痛い、もっと丁寧にやらんか」
介護士「いま、お茶出しますからね」
山崎 「今日の弁当はなんだこりゃ」
介護士「エビドリアみたいですよ」
山崎 「こんなもん食えるか、ばか。白い飯とみそ汁はないのか」
介護士M「山崎のおじいちゃんはずっと一人暮らし。息子さんも娘さんもまったく家に顔を出さないらしく、おそらくこの三年で会話をした相手はほとんど僕と、交代で担当している別のヘルパーだけだ」
山崎 「まったく、あの弁当屋はだめだ。わしの口に合わん。年寄りがこんなドリアンなんか食えるか」
介護士M「頑固で、気難しくて、笑った顔なんて一度も見たことがない。ヘルパーの間でも、山崎のおじいちゃんは評判が悪い。ある日のことだ」
山崎 「おい、ヘルパーさんよ。あんた若いからパソコン使えんだろう」
介護士「ええ、まあ」
介護士M「遺言状を考えたからパソコンで清書してくれ、と頼まれた」
介護士「そういうのは、専門家にお願いした方が…」
山崎 「いいから言われた通りにやれ」
山崎 「―したがって、次の通り遺産を相続することに決定した。ひとつ、久保陽介は現金および次の金融資産を取得する。新潟第一銀行本店の定期預金―」
介護士「はい、ええと、久保陽介は現金および―え、ぼ、僕? ちょっと待って―」
介護士M「意味が分からない。なぜ僕が遺産を受け取ることに?」
彼女 「えー、それすごいじゃん」
介護士「それも五千万もあるっていうんだよ」
彼女 「うそ。まじで? 超リッチじゃん」
介護士「どうしよう」
彼女 「くれるっていうんならもらっちゃえば?」
介護士M「五千万円あったら…。欲しかったバイクも車も買える。それどころか、家も買えるし、仕事を辞めて自分の会社だって作れる。それに…これまで安月給過ぎて自信がなかったけれど、お金にそれだけの余裕があれば…彼女にプロポーズができる。モルディブで結婚式を挙げるのが彼女の夢だ。でも…」
介護士M「赤の他人の僕が、人の遺産を勝手に相続していいのだろうか…」
介護士M「その日、一晩よく考えて、僕はおじいちゃんの家族の電話番号を調べ、事情を話した」
介護士M「翌々日の出勤日、普段通りに山崎のおじいちゃんの家を訪問すると、そこは大変な騒ぎになっていた」
山崎長男「冗談じゃないよ父さん、どういうつもりなんだ!?」
山崎次女「もうボケちゃったんじゃないの?」
山崎長女「ちょっとあんた、ヘルパーだかなんだか知らないけど、うちの父に何吹き込んだのよ?」
山崎次女「だからボケちゃったのよ」
山崎長女「横領じゃないのこれ」
介護士 「いや、僕はあの…」
山崎長男「非常識だ。こんな遺言無効に決まってる」
山崎次女「ボケたんだって」
山崎 「(遮って)ばーかーもん! わしが考えたことじゃ! 黙ってわしの言う通りにせい!」
一同 「…」

介護士M「おじいちゃんが家族のみんなを怒鳴りつけたとき、僕にはピンと来た。おじいちゃんの顔は、いままで見たこともないくらいに生き生きとしていた」
介護士「あの、僕は遺産をいただくつもりはまったくありません。おじいちゃんがこんな遺言状を作ったのはただの思いつき………たぶん、みなさんの顔が見たかったからだと思います」
介護士M「そうだよね、と顔をのぞくと、おじいちゃんは照れくさそうに目をそらした」
山崎 「あんたがもらってくれんというなら、しょうがない、息子たちに分けてやるか」
介護士M「家族が安心して引き上げた後、おじいちゃんは、いたずらっ子のような顔で僕に笑いかけた。それは三年間毎日のように通って、はじめて見る笑顔だった」
山崎 「すまんな。まあ、少しくらいなら分けてやってもいいぞ」
介護士「結構です(笑)」
製作・著作:BSN新潟放送
制作協力:劇団あんかーわーくす
脚本:藤田 雅史(ふじたまさし)